![]()

ここ長野県の佐久地域では、小鮒を甘露煮にして食べる風習がある。
みなさんはフナを食べたことがあるだろうか?
多くの現代人は、食べたことがないのではないかと思う。
なぜ、佐久地域ではフナを食べるのだろうか?
調べてみると、農林水産省にこんな記事を見つけた
- 歴史・由来・関連行事
県の東部に位置する佐久市は、群馬県との境に位置し、田んぼで淡水魚のフナやコイを飼えるほどきれいな水源に恵まれており、田んぼで水稲と一緒にフナやコイを育てる「水田養鮒」や「水田養鯉」などがおこなわれていた。それまで副産物として収穫していたフナだが、水田転作の進展とともにコイよりも手がかからないフナを養殖するようになった。地元では、9月になると5cm前後の小フナが生きたまま袋詰めされて販売される。町ではあちこちで「小フナ」の文字が見られた。小フナは、醤油と砂糖で甘辛く炊いて甘露煮にされる。買ってきた(若しくは、田んぼでとってきた)小フナを、水を何度もかえながらきれいに洗い生きたまま小フナを鍋に入れて調理する。柔らかくなるまで炊いたら、ほかほかの新米と一緒に食べる。小フナの僅かな苦みに秋の訪れを感じる。
海のない信州は、山に囲まれ、千曲川、木曽川、天竜川など豊かな水源に恵まれており、川や湖には淡水魚が育まれている。それをとって食べ、山の地域ならではの食文化が根付いていった。信州では川魚を昔から甘露煮にしておかずとして食べる風習がある。佐久の「コイの甘露煮」や諏訪湖の「ワカサギの甘露煮」なども信州の郷土料理として根付いており、丸ごと食べられる川魚の甘露煮は、カルシウムが豊富な上、昔は貴重なたんぱく源でもあった。
農林水産省 うちの郷土料理 より
9月一週目に小鮒の甘露煮を作る会にお呼ばれしたので、記録を残します。
フナは専門店のほか、スーパーマーケットでも売っているとか?
¥2500/kgと聞いたように思います、高級食材ですね…
材料:フナ1kg
醤油 1カップ
砂糖 300~400g
酒 1カップ
みりん 50~100ml
作り方①フナを買ってきて洗う(生きていることが大切)
②大きな鍋にフナとみりん以外の材料を入れて沸かす、鍋蓋も必要!
③グラグラ湧いている鍋に、湯呑み一杯分くらいのフナを入れてすかさず蓋を閉める
しばらくすると鍋の中のフナが静かになるので、フナを全て入れ終わるまで繰り返す
④全て入れたら蓋を外して中火で水分を飛ばす、灰汁があればとる
この時に絶対に箸などで混ぜないことが大切!
⑤粘りが出てきたらみりんを入れて照りを出し、完成!



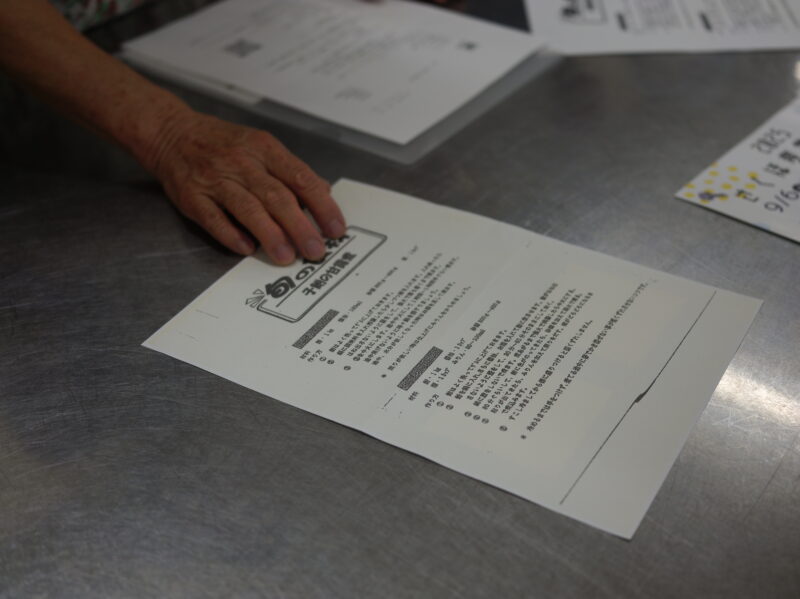
なぜ生きていることが大切かというと
「生きていると鍋の中で呼吸して、お腹の中に煮汁が入る(飲み込む)から」とのこと。
だからフナの苦味が抜けて、美味しくなるんだよ、と聞きました。
現代では、フナがかわいそうとか、動物愛護の観点から炎上しそうだなと思いつつも
民間伝承というか「そういうふうに生きてきた」文化が残っていることがとても尊いと感じたので、そのまま記事にします。
ちなみに、イナゴというバッタも食べるし、蜂の幼虫も私が幼少の頃(30年くらい前)には普通に祖父母の家の食卓にのぼっていた。
最近は田んぼにもめっきりイナゴはいなくなってしまったし、
蜂の子(と呼んでいた)も高級品なのではないだろうか。
長野は海がないし、山は深いしなかなか過酷な土地だったと思う。
現代は新幹線も高速道路だって通っていて、多くの人はお金を稼ぐ手段をもち、マイカーも持っている。
なにもフナじゃなくたって、スーパーマーケットに美味しいお刺身だって並んでいる。
それでもこの辺りの人の中には、これまで連綿と続いてきた文化を大切にしている方もいる。
どっちがいいとか悪いとかではなく、そういう文化的な景色を見せてもらえるのはとても幸せだなと立ち合わせてもらって感じました。
ちなみにお味は、ガツンと白米がススム系の甘露煮です。美味しいよ。
